社交のすすめ
かつてなく孤独を抱えた高齢者が多くいる社会で、人はどう老いの日々を過ごしたらよいのだろう?
話題の新著『 老いの思考法 』を上梓した、霊長類学者・山極寿一さんに訊く“老い方の知恵”。●社交とは、“明確な目的を持たない遊び”
――年々、高齢者の独居率の割合も増え続けていますが、超高齢社会において寂しさや孤独を抱えるお年寄りが大勢いる現状をどうご覧になっていますか。山極 これは僕があちこちで言ってるんだけど、日本社会から「社交」が消えつつあることに大きな問題があるんです。
社交とは、“明確な目的を持たない遊び”を指します。その遊びの中で、互いに共感力を発揮しながら、コミュニケーションをとって交流する時間が人間には必要不可欠です。一緒に詩を詠んだり、楽器を演奏したり、映画を鑑賞したりするのもいい。
人と人とがリアルに交流することが大切なんですね。
ところが今は趣味や好きなことをするさい、お金を払って一人で楽しんできて、一人で帰ってくることが多いでしょう。
それはただのエンタメの消費であって、社交ではない。人々が交流することを中心にした楽しい場を社会のなかで再構築しなければならないと考えています。――孤立したまま趣味の時間を楽しんできても、どこか満たされないものが残りそうですね。
山極 もちろん一人で楽しむ時間をすべて否定するわけではありませんが、本来、スポーツを楽しむのもコンサートに行くのも遊びの一環です。
その時間を誰とも分かち合わず、一人で完結してしまうのは非常にもったいない。その点、例えば「子ども食堂」は、食事を中心にした大変良い社交の場です。
今や全国で1万箇所を突破しましたが、こうした地域支援の場にボランティアで参加することは、優れた交流の機会となるでしょう。
地元のお祭りだってそう。準備に時間がかかるお祭りは、何ヶ月か前から計画をたて、関係各所さまざまな調整をし、催し物の練習をし、人々が協力しあって本番を迎える濃密な時間そのものです。文春オンライン
この対談を読んで皆さんはどのようにお考えであろうか。まあ学者先生の仰ることなのでごもっともだとは思うが…
そもそもこのインタビュアーの質問の仕方からして、孤立や孤独を否定的に見ているのがありあり。
『――孤立したまま趣味の時間を楽しんできても、どこか満たされないものが残りそうですね。』
わたしはむしろ、こんな風に他人の趣味の楽しみ方にケチを付ける輩がいるからぼっちの時間を選んでいるのだがʅ(◞‿◟)ʃ
人の心が満たされているとかいないとか…いったい他人様がどうやって推しはかることが出来るというのだろう。
山極さんは、ゴリラ研究の第一人者として知られ、京都大学前総長であり、現在は総合地球環境学研究所所長を務めているという。
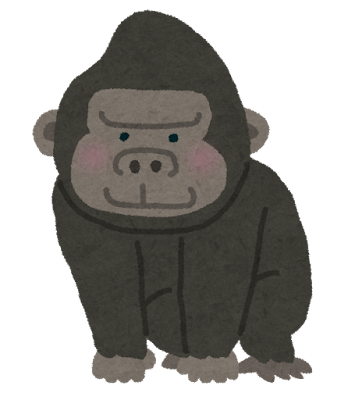
山極さんがゴリラを研究した理由は、「人間から一歩離れて人間を見つめてみたかったから」だそう。
きっと凡人のわたしなど及びもつかないような高みから、今のこのご時世を憂いておられるのであろうが…少なくともわたしは、ひとり時間でどこか満たされないと感じたこともないし、その時間を誰かと分かち合わなかったからといって孤独を感じたこともない。
なので当然、その時間をもったいないと考えたこともなく、逆にそんな時間こそが豊かな時間だと感じている。
彼が例に挙げている趣味のあり方にしても、“一緒に詩を詠んだり、楽器を演奏したり、映画を鑑賞したりするのもいい。人と人とがリアルに交流することが大切なんですね。“
たとえば映画を観るなんてことも、一時ママ友とよく出掛けていたこともあったが、いつのまにか行かなくなっていった。かと言って彼女と疎遠になったわけではない。
そもそも美術、音楽、映画を鑑賞する行為自体、その“作品と自分との対話“であるから、その前後に食事をしたり、お茶をしながら感想を話すなど共通の話題で盛り上がることはあっても、それは個人個人がそれぞれの時間を愉しんだ後の感想戦のようなものだと思っている。
むしろ孤立した時間を経て、その理解が深まっていくものではないだろうか。
子ども食堂
そして、このインタビュー前段の“日本に「社交」が消えつつある“という論点から、いきなり「子ども食堂」は良い社交の場という展開に…もうすっかり鼻白らむ思いがした。
これって最近の陰謀渦巻くドラマの見過ぎかもしれないが、ちょっとした“社交の場“にはマルチや宗教がうようよいるから近づかないっていう精神が染みついているので、「子ども食堂」という一見まともそうなボランティア活動にもそんな危険が潜んでいるのではないかと、疑ってかかってしまう自分がいる。
で更に…この山極さんの現在の肩書きを見てみるとさらにもやもやするものを感じざるを得なくなってきてしまう。
なんと、まもなく開幕を迎えようとしているあの問題山積の大阪・関西万博「シニアアドバイザー」なるものに名を連ねているのである。
うわーこれって報酬はおいくら?とググってみると…なんと非公表なんです!!
この非公表の意味するところを考えると、また一層もやもやしてしまう。
おそらくボランティアだとしたら、はっきり無報酬とアナウンスされていると思うのですが、そうではなく、非公表というところに闇を感じてしまうわたしの心ってやっぱり汚れているのかしら(笑)
まあ、そんなことはどうでもいいことだが…あの問題だらけの万博の運営側に名を連ね、高みの見物してるお立場の方から、わたしのぼっちな趣味は正しくないと否定されても、それはもう大きなお世話だと言わざるを得ない。
こういう人って、群れない=コミュ障という…ステレオタイプな価値観を信じて疑わない俗にいう昭和なおっさんなんじゃないかしら。知らんけど(* ´艸`)
ついでに言ってしまうと、人間とゴリラは生物学的に言えば霊長類という同じカテゴリーに分類されるのかもしれないが、その権威の大先生だからといってその方が人間について全て正しく把握しているかといったら違うだろうということ。
やっぱり人間はゴリラとは似て非なる生き物であり、またそれぞれの種で日々進化し、変化していく生き物なのだ。それは花の種も年々進化し、環境に順応出来ないものはやがては淘汰されてしまうのに似ている。
一昨年購入したヒヤシンスとムスカリとチューリップの寄せ植え。花後にチューリップの球根だけ掘り出し、残りはそのままで3度目の春を迎えた。当時は2、3個しか咲いていなかったムスカリが、今年はもう数え切れないぐらいに増えて、ほぼヒヤシンスを駆逐するのではないかというぐらいの勢い。

最初は孤独だった花もその土地に順応し、次第に自分の居場所を広げていくように…人もまた自分の心の赴くに任せていれば、いつかきっと安寧の地に辿りつけるのではないだろうか。
今年はまた、杉の木の下に植えた芝桜が順調に増殖してくれてたくさんの花を咲かせてくれた。

その姿があまりにも美しくまた健気だなあと思っていたところ、お友達ブロガーのMayaさんの記事の一句に触発され、またわたしも一句。
昼間から
羊数える芝若し
Mayaさん 雨を数え、羊数える より
返句 “ 雨宿り しずく染み入る 芝桜“
素敵な句には、やはり自分の言葉を返したくなる。
意義や充足や精神や心の何かしらの手ごたえを
感じることが趣味であり、
感じないのが消費的な遊び。
どちらを選ぶかも人それぞれである。




コメント